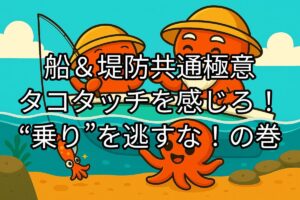はじめに
船タコ釣りは、日本各地の海で楽しめる人気の釣りですが、その多くは「底を釣る」ことが前提となります。タコは海底付近で活動し、岩や障害物、海藻に身を潜め、目の前を通る餌やルアーに抱きついて捕食します。このため、着底を感じて底ベタで誘うのがセオリーとされてきました。
しかし、根が荒いエリアでは話が違います。底ベタでズル引きすると、数投で根掛かりの連続。タコを釣るどころか、仕掛けばかり失うことになりかねません。そんな難所でこそ生きるのが「底から約10センチ浮かせる」釣り方です。
 タコボーイ
タコボーイ10センチも浮かせたら、タコが抱かないんじゃないの?
 タコ仙人
タコ仙人それが違うんじゃ。ワシも何度も試したが、10センチ浮いててもタコは抱きつく。むしろ根掛かりが減る分、釣りが続けられるので、結果として釣果もあがるのじゃ。
底から「10cm浮かせ」が有効な理由
- 根掛かり回避効果:ゴロタ石や段差を越えやすく、オモリが岩の間に挟まりにくい
- タコの捕食レンジに留まる:タコの腕は長く、10センチ程度なら容易に伸ばして抱く
- 潮の流れで自然なアピール:浮かせた状態で潮に乗せると、エギがヒラヒラと自然に動く
この理論は多くの実戦記事でも紹介されていますが、私自身の釣行経験からも断言できます。「底からわずかに浮かせても、タコは十分に釣れる」という事実です。数え切れないほど根掛かりに悩まされた現場で、この方法に切り替えてから釣果と回収率が劇的に向上しました。
浮かせっぱなしはNG
ここで注意すべきは「浮かせっぱなし」です。ずっと浮かせていると、今どれくらい底から離れているのか感覚が鈍り、知らない間に高く上がりすぎてしまいます。こうなるとタコのレンジから外れてしまい、アタリが激減します。
対策は簡単。数十秒ごとに底を取り直し、そこから10センチだけ浮かせるというサイクルを繰り返すことです。こうすることでレンジを安定させ、根掛かり回避と釣果の両立が可能になります。
 タコ仙人
タコ仙人浮かせっぱなしは底からの距離感を失うから注意が必要じゃ!
 タコボーイ
タコボーイだから底取りをちょこちょことやるんだね!
 タコ仙人
タコ仙人潮の流れ、船の流れ、波、深さ、底地の質、こうした様々な変化を常に感じながらエギをコントロールできれば、一人前のタコ釣り師じゃよ✨
道具と仕掛けの基礎
竿
操作性の高い船タコ専用竿がおすすめ。短め(1.6〜1.9m)でバットパワーがあり、穂先は柔軟にアタリを取れるタイプが理想です。
リール
小型ベイトリールで十分。パワーハンドル搭載モデルだと回収時や根掛かり外しで有利。
ライン
PEライン1.5〜2号を基準に。リーダーはフロロ5〜6号で、根ズレ対策を意識します。
オモリ
潮の速さや水深に合わせて30〜50号を使い分け。スティック型は根掛かり回避に有効。
エギ
カラーは日照や水色に合わせて使い分け。根が荒いポイントでは派手色でアピール。
「浮かせ釣り」の動作手順
- 着底を感じる
- 竿先をゆっくり持ち上げ、10センチだけ浮かせる
- 潮に乗せてゆっくり流す(時折軽くシェイク)
- 数十秒ごとに底を取り直す
- アタリがあれば即合わせ、ズシっと重みがあれば巻き上げ
会話で学ぶ浮かせ釣りのコツ
 タコボーイ
タコボーイエギを浮かせるとタコが見つけてくれない気がする…
 タコ仙人
タコ仙人それが少し浮かすくらいなら、ほぼ問題ないのじゃ。タコの腕は長いし、嗅覚も鋭い。10センチ浮いてても、匂いと動きで抱いてくるぞ。それよりも根が荒い場所でヅルヅル引いて根がかりを連発してる方が、仕掛けも時間もロスが大き過ぎるぞ
 タコボーイ
タコボーイなるほど~!じゃあ根掛かりも減って、一石二鳥なんだね!
 タコ仙人
タコ仙人そうじゃ。釣りは仕掛けを水中(タコのいるレンジ)に残せる時間が長い者が勝つんじゃ。
10cmを安定してキープするための竿さばき
海の上では、潮流・風・波の影響で仕掛けの高さは常に変化します。その中で10cmという微妙な浮かせ量を維持するには、感覚だけでなく視覚と反応の両方を使ってコントロールすることが重要です。
- 竿先はやや立てて構える:潮や波の変化に柔軟に即応できる
- 船の上下動に合わせて竿先を軽く動かす:エギが急に跳ねないようにする
- 潮が緩いときは竿先を低めにしてステイ時間を延ばす:アタリを待つ余裕が生まれる
- 縦小づきで高さを修正:オモリが底を叩く感覚で微調整
 タコボーイ
タコボーイ10cmってどうやって感覚をつかむの?
 タコ仙人
タコ仙人最初は難しいが、底を感じたら竿先を2〜3cm分だけ持ち上げる感覚で始めればええ。それを潮や波に合わせて調整していくんじゃ。
ライン角度管理と根掛かりの関係
ラインが垂直に近いほど、仕掛けは真下に入り、根掛かりが減ります。逆に潮や風で角度がつくと、オモリが底を引きずりやすくなり、岩の隙間に引っかかる確率が高まります。
このときの対策は次の3つです。
- オモリを重くする:角度を立てやすくする基本手段
- 少し大きめに浮かせる:岩や段差をやり過ごす回避方法
- 潮が速すぎる場合は何もしなくても仕掛けが浮く:むしろ浮かせ量を減らす方が安定する
潮と波に応じた竿の高さ調整
潮が早いとき、竿をやや高めに構えるのは仕掛けの高さを細かく調整しやすくするためです。これは波による船の揺れでも同じ理由で、上下動に対して竿先を柔軟に動かせる調整余力を持たせることが目的です。
竿先を高く構えていれば、波が来てもすぐに高さを戻せますし、潮の変化にも即座に対応できます。高さを取るのは「見栄え」ではなく、操作の余裕を作るための戦術なのです。
 タコ仙人
タコ仙人潮も波も竿の高さで制すんじゃ。
 タコボーイ
タコボーイただ上げてるんじゃなくて、余裕を持つためなんだね!
地形変化を察知して回避する
実戦記事でも、そして私の経験からも、根がきつい場面ではオモリやエギを底から離して縦小づきで上下させ、地形変化を察知したらすぐ持ち上げて回避するのが効果的です。
例えば、底が急に硬くなったり、手元に「カンッ」という感触が伝わった瞬間、それは岩や段差の可能性が高いです。このときためらわず竿を上げれば、根掛かりを防ぎつつ、その段差に潜むタコを狙えます。
潮向きと船の流し方
- 道具が潮下へ流れていく(エギが船から離れる): 底を切らさないように最低限の送り込みで調整。常に糸を張ってテンションを保つことで、仕掛けが流されすぎず、アタリも明確に感じられる。糸を出しすぎるとすぐに横や後ろの人とオマツリになるため注意。
- 道具が潮上側に切れ込む(エギが船に近づく): 前方(潮上)へ軽くキャストして距離を作り、手前に寄る間は糸のたるみを取ってテンションを保ちながらタコの重みや違和感を感じ取る。船下に入りそうなときは早めに回収して入れ直す。
- 横潮やドテラ流し: 片舷が潮先になりやすく有利だが、潮下側は根掛かりやオマツリのリスクが高い。投入位置を潮上寄りにずらし、やや重めのオモリで仕掛けを立たせ、糸を張って流されすぎを防ぐ。
ポイント: 船タコ釣りの基本は「底を釣る」釣り。今回、根が荒い場所での釣り方・コツとして、底から10cm浮かせた釣り方を説明してますが、潮向きがどうであっても、糸を張って仕掛けを流されすぎないよう管理し、底から離れすぎないことが釣果アップの鍵です。
仕掛けバリエーションと使い分け
- ダブルエギ:アピール力アップ、ただし重量増で潮の影響を受けやすい
- トリプルエギ:最大アピールだが根掛かりリスクも高く、上級者向け
- オモリ形状:スティック型は根掛かり回避に優れ、丸型は回収率が高い
 タコ仙人
タコ仙人ちなみに、、、アピール力を高める為に、オモリにもラバーをセットしたりするのも使えるぞ!
浮かせ釣りと底ベタ釣りの切り替え
根掛かりが多発するエリアでは浮かせ釣り、砂地や根が少ないエリアでは底ベタ釣り。状況に応じた切り替えで効率よく釣果を伸ばせます。
 タコボーイ
タコボーイ今日は浮かせでいく?
 タコ仙人
タコ仙人根の荒れ具合を見て決めるんじゃ。釣り方は一つじゃないぞ。
地域別の有効性と使い分け
① 明石エリア
明石海峡周辺は砂地が多く、根掛かりリスクが低いため、基本は底ベタ釣りが有効。根周りをピンポイントで攻めるときや漁礁周りでは浮かせ釣りが効果を発揮する。
② 東京湾内の岩礁帯
ゴロタ石や漁礁が点在し、底ベタでは数投で根掛かり。浮かせ釣りを主戦術として、潮や風に合わせて浮かせ量を調整するのが常套手段。
③ 瀬戸内海の島周り
砂地と根が入り混じる複合底質エリア。砂地は底ベタ、根周りは浮かせとハイブリッド運用が必要。
④ 日本海のゴロタ浜沖
大きな岩が点在し、段差越えやミゾ越えが頻発。浮かせ釣りを基本に、竿さばきで地形変化を常に回避する意識が求められる。
 タコボーイ
タコボーイ同じ船タコ釣りでも、場所によって全然違うんだ!
 タコ仙人
タコ仙人底質を読む、感じることが、釣り方を選ぶ第一歩じゃ。
よくある失敗とその改善方法
① 浮かせすぎ
10cm以上浮かせるとタコの捕食レンジから外れる可能性大。常に底を意識して微調整。
② 浮かせっぱなし
浮かせたままだとレンジ感覚が狂い、知らぬ間に高く上がってしまう。数十秒ごとの底取りが必須。
③ 横引きのしすぎ
潮や風で仕掛けが横に流れると根掛かりしやすい。縦小づき主体でコントロール。
④ 状況無視の釣り方固定
潮が速いときはオモリ変更、浮かせ量調整、竿を高く構えて調整余力を持たせる。波による船の揺れにも同じ対応が有効。
応用テクニック
① 着底直後の「間」
着底してから1〜2秒止めるとタコが抱く時間を与えられる。ただし根掛かり多発エリアでは慎重に。
② 潮変わり直後の集中攻撃
潮が変わった直後はタコの活性が上がることが多く、短時間で釣果を伸ばせるチャンス。
③ 安定ドリフト攻め
風・潮・仕掛けのバランスが合えば、仕掛けが自然に流れる安定ドリフト状態を作れる。この状態では上下の小さな誘いを加えるだけで効果的にアピールできる。
④ カラー・サイズチェンジ
同じポイントでアタリが止まったら、エギの色やサイズを変えてスレ対策。
根掛かり回避の最終手段
- テンションを抜く:ラインを緩めてオモリを自然に外す
- 逆引き:船を少し動かし、反対方向から引く(乗合船では難しい)
- ラインを弾く:軽く弾くことで針が外れることもある
 タコボーイ
タコボーイ根がかりしたと思ったら針が曲がって帰ってきた!
 タコ仙人
タコ仙人直せばまた使えるぞ。堤防釣りだと太いラインを使って、針を曲げて回収する釣り方が有効なくらいじゃ。ちなみに針先刺さりにくくなるので、シャープナー等の針を研ぐ道具を持っておくと良いぞ
まとめ
- 底ベタ釣りが基本だが、根が荒い場所では10cm浮かせ釣りが有効
- 浮かせっぱなしは避け、こまめに底を確認
- ライン角度管理と潮・波への対応が根掛かり減少のカギ
- 竿を高く構えて調整余力を持たせることで安定性アップ
- 地域や状況に応じて釣り方を切り替える柔軟さが必要
この戦術を理解して実践すれば、根が荒い難所でもタコとの駆け引きを楽しみながら、確実に釣果を伸ばすことができます。現場での経験と合わせて、このテクニックを自分の武器にしてください。
📚 関連記事